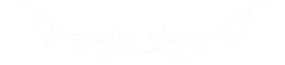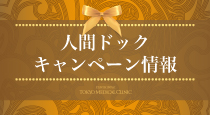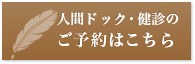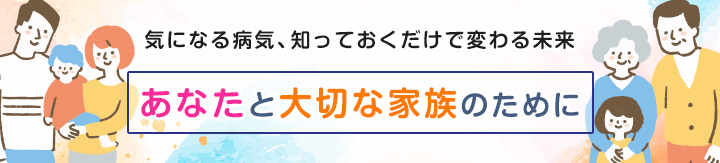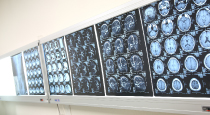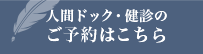尿酸 (血液)
基準値
| 基準値 | 2.1~7.0mg/dL |
|---|
この検査で疑われる病気
- 高値:高尿酸血症(痛風)、腎不全 等
細胞が分解された後にできる老廃物で、通常は尿中に排泄されますが、腎機能が低下したり、プリン体を多く含む食品をとりすぎたりすると、血液中に増加します。尿酸値の高い状態が続くと、尿酸の結晶が足の親指の間接などにたまり、激痛を伴う痛風発作を引き起こします。
尿酸値が8.0mg/dlを超えると治療が必要となるのは、今後「痛風」になるリスクが高まるためです。尿酸値が7.0mg/dl以上の数値が数年続くと「痛風」を発症しやすくなります。
「痛風」だけでなく「高尿酸血症」の状態がすでに危険であるため、数値を下げるよう努めなくてはなりません。
治療は、生活の見直しと併せて薬物治療を行います。尿酸値が8.0mg/dlは薬物治療が推奨される数値、9.0mg/dlを超えると必須の数値となります。
尿酸の役割と代謝の概要
- 尿酸は、プリン体という物質が分解される際に肝臓で作られ、最終的に血液中に放出されます。
- 尿酸の約3分の2は腎臓から尿として排泄され、残りは腸から排泄されます。
- 尿酸の産生量と排泄量のバランスが崩れると、血液中の尿酸濃度が高くなります(高尿酸血症)。
尿酸値が高くなる主な原因
(1) 尿酸の過剰産生
-
プリン体の過剰摂取
- 食事中のプリン体が多い食品を摂取すると、尿酸の産生が増えます。
- プリン体が多い食品:
- 肉類(特にレバーや赤身肉)
- 魚介類(イワシ、マグロ、アンコウの肝など)
- アルコール(特にビールや日本酒)
-
代謝異常
- 遺伝的要因や代謝異常によって尿酸の産生が増える場合があります。
- 痛風を引き起こしやすい体質の人は、このカテゴリーに入ります。
-
激しい運動
- 激しい運動により、エネルギー代謝が活発化して尿酸が過剰に産生されることがあります。
-
細胞の急激な崩壊(プリン体の放出)
- 細胞が急激に壊れる病気や治療の影響で尿酸値が上がることがあります。
(2) 尿酸の排泄低下
-
腎機能の低下
- 腎臓が尿酸を十分に排泄できないと、血液中の尿酸濃度が上昇します。
- 慢性腎臓病(CKD)や腎障害がある場合に頻繁に見られます。
-
アルコール摂取
- アルコールは尿酸の産生を促進し、さらに腎臓からの尿酸の排泄を抑制します。
-
薬剤の影響
- 一部の薬剤は尿酸の排泄を妨げます。
- 利尿剤(チアジド系やループ系利尿剤)
- アスピリン(少量服用時)
- シクロスポリン(免疫抑制剤)
-
脱水や水分不足
- 水分が不足すると尿量が減少し、尿酸の排泄が低下します。
-
内分泌異常
- 一部の内分泌疾患(甲状腺機能低下症、副甲状腺機能亢進症)で尿酸値が上昇する場合があります。
-
高血糖・インスリン抵抗性
- 糖尿病や肥満によるインスリン抵抗性が、尿酸の排泄を妨げることがあります。
(3) 生活習慣や環境要因
-
食生活の乱れ
- 高プリン体食品や高カロリー食品、砂糖を含む飲料(特に果糖を多く含む飲料)の過剰摂取。
-
肥満
- 肥満は尿酸の産生を増やし、排泄を妨げます。
-
ストレス
- ストレスが尿酸値を一時的に上昇させることがあります。
特定の疾患が原因で尿酸値が高くなる場合
-
痛風
- 高尿酸血症が続くと、尿酸結晶が関節に沈着して炎症を引き起こします。
- 痛風発作は激しい関節痛を伴います。
-
尿路結石
- 尿酸が過剰に排泄される際、尿中で結晶化し、尿路結石を形成することがあります。
-
代謝性疾患
- メタボリックシンドロームや糖尿病と関連する場合があります。
-
腫瘍崩壊症候群
- 抗がん剤治療中に腫瘍細胞が壊れることで尿酸が急激に上昇することがあります。
尿酸値を下げるための予防と対応
-
食事改善
- プリン体を多く含む食品やアルコールの摂取を控える。
- 野菜や果物、乳製品を多く摂取する。
- 水分を十分に摂取し、尿酸排泄を促進。
-
運動
- 適度な運動で肥満を防ぐ。ただし、過度な運動は逆効果。
-
禁酒または適度な飲酒
- 特にビールや果実酒の摂取を控える。
-
薬物治療(必要な場合)
- 尿酸産生抑制薬(アロプリノール、フェブキソスタットなど)。
- 尿酸排泄促進薬(プロベネシドなど)。
-
定期的な血液検査
- 尿酸値を定期的にチェックし、適切にコントロール。
尿酸値が高い場合は、早めに医師に相談し、生活習慣の改善や必要な治療を受けることが大切です。痛風発作や合併症を防ぐためにも、注意深く管理しましょう。
お気軽にご予約・お問い合わせください
お電話からのご予約